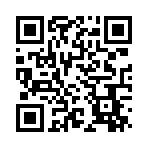建中寺はまるで西洋の教会のようにおおらかだ。
江戸時代に入ってから多くの寺社建築が日本国中に建設された。
建中寺もそのなかの一つである。
名古屋市東区にある建中寺は1651年江戸時代初期に徳川義直の菩提を弔うため作られた。
現在の総門の位置が建中寺公園を挟んであることからも、
当時の規模が相当に大きな寺院だったことがうかがえる。

総門を見上げると屋根を支える梁が美しく架けられている。
シンプルな構造だが耐久性と材料の美しさ加工の美しさ
門としての端正な作りが見栄えする。

山門までの間は現在は公園になっているが
自由にそこで休憩できることで憩いのスペースになっている。
近くにコンビニがあるのでパンと牛乳を買って
山門を見ながらベンチで昼食をとるのも初めてのことではない。
昼食を古寺の見える公園でとるのは頭がすっきりして楽しい。

湧き水のオブジェを見ながら癒しの時間を楽しんでいると、
鳩がものほしそうに近寄ってくる。
平和の象徴でよいのだが、絶対にパンはやらない。
それには理由がある。

山門を見上げると軒先をささえる見事な組み物がある。
四角いお酒のますのようなブロック、
斗(ます)と呼ばれるパーツを
ひじを曲げた腕のような形の肘木(ひじき)が支えている。
何段にも重なる姿はとても見ごたえのあるものだ。
当時の建築技術を存分に発揮して組み立てられたその姿が、
金網で邪魔されているではないか。
これは、よくある風景で、おそらく鳥が住まないようにあるのだ。
そのために、ちょっとだけ見えにくいのが残念。
だから、鳩にはえさはあげないのだ。

門をくぐると本堂がある。
私は建中寺は現在が理想的な状態だと思うが、
それは、キリスト教会のように自由に気兼ねなくお堂に入り、
本尊の阿弥陀仏と向き合うことができるからだ。
このぐらいの規模になると寺のがらんどうも非常に大きく、
周りに人がなければほぼ一人で占有できる贅沢な状態になる。
ただ、人気の多い寺の場合、多くの集まった人の話し声で静けさがなくなる。
その空間の持つ雰囲気も台無しといったところだ。
この点、建中寺のお堂の中は大きく内部もまさに
人間が何も考えない時間を過ごすのに最適な場所だ。

建中寺の場合、ちょうどよい具合に人気がなく静かで、
本堂の外に出ると幼稚園から子供の声がするぐらい和やかだ。
境内の鐘楼もまた文化財のうちのひとつ。
本堂の内部に襖絵があるが個人的にはその構図が好きである。
白い獅子の体は仁王像の腹筋のような躍動感があり、
飛びあがる姿に合わせて左の花の形が韻を踏むように寄り添って対となっている。
簡単に言うと遠めに見るとおなじ様な形になって見えるということだ。
観光地で襖絵を見るときは鳥獣と草花や岩の形が同じ形や角度など
スピード感を合わせているのを読み取っていくと楽しみが増す。

経蔵は真っ白に塗られているため古さを感じないが
江戸時代に建築された文化財である。

本堂横の明王殿不動堂の中に尾張徳川家の秘仏である
不動明王が本尊としてある。普段は見えない奥にあるようだ。
建中寺の不動堂は東海三十六不動尊霊場のひとつで、
目立たないが密かなパワースポットである。

開山堂は江戸時代に再建された建築で不動堂の向かって右にある。
建中寺の境内は非常に入りやすく参拝もしやすい。
公園と隣接したり、幼稚園があることで身近になり
一つ一つの建築と向き合うのにも気兼ねない。
このスタイルの寺はとても好きである。
古寺はこのようにオープンでいつもパワーをもらえる場所であってほしい。
大きな地図で見る
建中寺もそのなかの一つである。
名古屋市東区にある建中寺は1651年江戸時代初期に徳川義直の菩提を弔うため作られた。
現在の総門の位置が建中寺公園を挟んであることからも、
当時の規模が相当に大きな寺院だったことがうかがえる。
総門を見上げると屋根を支える梁が美しく架けられている。
シンプルな構造だが耐久性と材料の美しさ加工の美しさ
門としての端正な作りが見栄えする。

山門までの間は現在は公園になっているが
自由にそこで休憩できることで憩いのスペースになっている。
近くにコンビニがあるのでパンと牛乳を買って
山門を見ながらベンチで昼食をとるのも初めてのことではない。
昼食を古寺の見える公園でとるのは頭がすっきりして楽しい。

湧き水のオブジェを見ながら癒しの時間を楽しんでいると、
鳩がものほしそうに近寄ってくる。
平和の象徴でよいのだが、絶対にパンはやらない。
それには理由がある。

山門を見上げると軒先をささえる見事な組み物がある。
四角いお酒のますのようなブロック、
斗(ます)と呼ばれるパーツを
ひじを曲げた腕のような形の肘木(ひじき)が支えている。
何段にも重なる姿はとても見ごたえのあるものだ。
当時の建築技術を存分に発揮して組み立てられたその姿が、
金網で邪魔されているではないか。
これは、よくある風景で、おそらく鳥が住まないようにあるのだ。
そのために、ちょっとだけ見えにくいのが残念。
だから、鳩にはえさはあげないのだ。

門をくぐると本堂がある。
私は建中寺は現在が理想的な状態だと思うが、
それは、キリスト教会のように自由に気兼ねなくお堂に入り、
本尊の阿弥陀仏と向き合うことができるからだ。
このぐらいの規模になると寺のがらんどうも非常に大きく、
周りに人がなければほぼ一人で占有できる贅沢な状態になる。
ただ、人気の多い寺の場合、多くの集まった人の話し声で静けさがなくなる。
その空間の持つ雰囲気も台無しといったところだ。
この点、建中寺のお堂の中は大きく内部もまさに
人間が何も考えない時間を過ごすのに最適な場所だ。

建中寺の場合、ちょうどよい具合に人気がなく静かで、
本堂の外に出ると幼稚園から子供の声がするぐらい和やかだ。
境内の鐘楼もまた文化財のうちのひとつ。
本堂の内部に襖絵があるが個人的にはその構図が好きである。
白い獅子の体は仁王像の腹筋のような躍動感があり、
飛びあがる姿に合わせて左の花の形が韻を踏むように寄り添って対となっている。
簡単に言うと遠めに見るとおなじ様な形になって見えるということだ。
観光地で襖絵を見るときは鳥獣と草花や岩の形が同じ形や角度など
スピード感を合わせているのを読み取っていくと楽しみが増す。

経蔵は真っ白に塗られているため古さを感じないが
江戸時代に建築された文化財である。

本堂横の明王殿不動堂の中に尾張徳川家の秘仏である
不動明王が本尊としてある。普段は見えない奥にあるようだ。
建中寺の不動堂は東海三十六不動尊霊場のひとつで、
目立たないが密かなパワースポットである。

開山堂は江戸時代に再建された建築で不動堂の向かって右にある。
建中寺の境内は非常に入りやすく参拝もしやすい。
公園と隣接したり、幼稚園があることで身近になり
一つ一つの建築と向き合うのにも気兼ねない。
このスタイルの寺はとても好きである。
古寺はこのようにオープンでいつもパワーをもらえる場所であってほしい。
大きな地図で見る